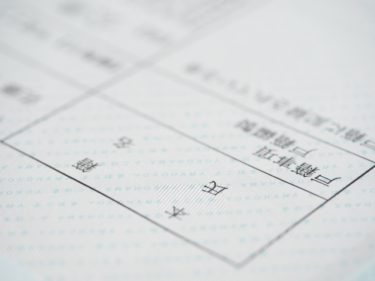いつも急に訪れるお通夜。
もともとは故人の親族や友人など人たちが一晩中故人に付き添い、邪霊の侵入を防ぎ最後の別れを惜しむ儀式でした。
そんなお通夜の正しいマナーをしっていますか?
おそらく「正しい?」と言われると不安になる方もいるかもしれませんので、お通夜のマナーについて書いていきましょう。
お通夜とは?
お通夜は夜通し灯りを消さずに故人を見守る儀式です。
葬儀や告別式の前夜に親族や親しい友人などゆかりの深い人が集まって故人の冥福を祈り、別れを惜しむのです。
遺族は灯りと線香の日を絶やさぬようにします。
一般的には亡くなった翌日に弔問客を迎えてお通夜を行い、翌々日に告別式と葬儀というにっていを決めるのですが死後24時間は火葬や埋葬をしてはいけないということが法律で定められていますので、遺体をしばらくは安置をしなければなりません。
お通夜の時間
お通夜の時間は告別式の前日が一般的。
時間は告別式の前日の18~19時からはじまり通夜ぶるまいが終わるのは21~22時ごろという時間帯が一般的となっています。
最近は夜のうちにお開きとなる「半通夜」が主流となっていますね。
身内の場合は通夜の準備をできる限り手伝い、通夜の開始前には遺族席について弔問を受けます。
そうではなくて、通夜に参列をする場合には弔問に伺う時間は早すぎても遅すぎても迷惑となります。
目安としては定刻の10分前に到着をするくらいがよいでしょう。
お通夜の流れ
そんなお通夜の流れを頭に入れておきましょう。
一般的な流れについては以下のようになっています。
1,受付
2,一同着席
3,僧侶入場・読経
4,焼香
5,僧侶退場
6,喪主挨拶
7,通夜ぶるまい
ちなみに座る場所はどこでもよいです。
祭壇近くは向かって右側に遺族、親族、左側に弔問客の席ですので一般の会葬者は正面を向いた席に座るのが一般的です。
祭壇に近いほうが上座となりますが、混雑をしてくると入り口近くに人があふれる場合もありますのでスムーズな式の運びの妨げにもなるため席にはこだわらず座りましょう。
通夜ぶるまいの対応
通夜ぶるまいとは親族や故人にゆかりのある人が故人を偲んで軽い軽食をすることです。
故人への供養の意味もありますので引き止められたら出席をし、ひと口でも箸をつけるのがマナーとなります。
ただし、お酒も出されますが酔うのは厳禁です。
また、親族は次に日の葬儀の準備もあるためあまり長居をするのはよくありません。
お通夜のマナー
次にお通夜のマナーについて書いていきましょう。
服装や香典など知らないことも多いので書いていきますね。
服装
基本は男性女性関係なく、喪服を着用するのがマナーとなります。
男性の服装
そのため男性は「ブラックスーツと白のシャツ、黒無地のネクタイ、黒のベルト、黒の靴」となりますね。
シングル、ダブルはどちらでも可能ですがタイピンやポケットチーフはマナー違反となります。
時計やハンカチも地味なものにしておき、ゴールドの金具は原則不可となります。
女性の服装
女性は和装の場合は黒無地で羽二重で洋装の場合はフォーマルスーツもしくはワンピースで長袖が原則ですがパンツスーツでも問題はありません。
スカートは膝下丈、ボタンやベルトのバックルなども黒い布でくるであるものが正式ですね。
バッグは黒のフォーマルバッグを利用し、皮やファーの素材は殺生を意味することからマナー違反です。
アクセサリーは結婚指輪とパールは問題ありませんが、二連、三連のものは「不幸が重なる」という意味を持つのでマナー違反となります。
男女ともに髪の毛も奇抜なものは控えておき、香水もキツイ香りはNG。
女性は髪の毛の飾りも地味にしておきましょう。
長袖が基本?
また、肌の露出することはお悔やみの席ではふさわしくないと言われています。
そのため、基本は長袖となりますが最近は夏用の涼しげな夏服も用意をされていますので、できれば大人のマナーとして夏用礼服も用意をしておきましょう。
キリスト教式の対応
初めてキリスト今日のお葬式に行く場合には服装に迷うこともありますが、キリスト教でもやることは同じなので理解をしておきましょう。
ただし、焼香はないのでやり方がかわるため指示に従いましょう。
日本ではめったにキリスト教式を行うことはありません。
香典の渡し方
香典は受付で渡すことになります。
最近は受け取らないところも多いですが、一応持っていっておくことはマナーとなりますね。
受付で最初に「心からお悔やみ申し上げます」とお悔やみの言葉を述べてから名簿に記帳をします。
香典は表向きの向きを先方へ向けて両手で渡します。
香典はふくさに包んで持参をするのが正式なマナーとなりますが、ふくさがない場合には地味は色の小風呂敷でも問題はありません。
焼香のやり方
あと、お通夜といえば焼香が必ずといってよいほどありますが、やり方って前の人をみてマネしています。
おそらく、そうやっている方は多いと思いますので正しいやり方についても書いていきましょう。
立礼焼香
どちらかと言えばこちらが一般的の立って焼香をするという方法になります。
1,遺族と僧侶に一礼をして祭壇へ進みます。
2,遺影へ向かって一礼をして合掌をします。
3,右手で抹香をつまみ、自分の目の高さにささげて香炉へ戻します。(1~2回くらい)
4,遺影で合掌。遺族と僧侶にも一礼をして席に戻ります。
回し焼香
これは席に順番に焼香が回ってくるものです。
1,焼香が回ってきたら軽く一礼をして受け取ります。
2,焼香を自分の前に置き、焼香をします。抹香をつまんで目の高さで1~2回ご冥福をささげ、香炉へ戻します。
3,焼香後は次の人へ軽く一礼をして渡します。
お通夜のまとめ
お通夜は急に訪れるものです。
しかし、そこのマナーを知っているからこそ社会人として恥ずかしくないものですね。
若いうちならば許されることも立派な大人になると許されないものなのでしっかりと理解をしてお通夜に臨みましょう。
参列の場合は悲しい遺族に寄り添うのがマナーとなりますので控えめな態度で失礼のないように気を付けてくださいね。